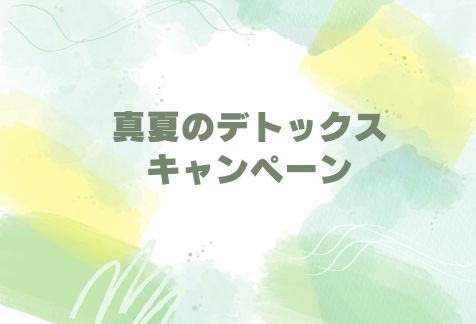カテゴリ:
皆さま、こんにちは。 渋谷セントラルクリニックの大友博之です。
今月は、6月に登壇いたしました「THAILAND WELLNESS & HEALTHCARE EXPO 2025」での講演内容を中心にお届けしたいと思います。
この国際エキスポは、タイ政府が国家戦略として推進するウェルネス産業の一大プロジェクトであり、大臣級の要人も登壇する、まさに“国を挙げた次世代医療の発信拠点”と呼べる場です。
私はそのイブニングセミナーにて、「Longevity Cocktail Therapy(長寿カクテル療法)」という テーマでお話をさせていただきました。
これは私が、これまで20年以上にわたって臨床と研究を続けてきた「抗加齢医学」と「再生医療」を統合する、いわば“21世紀型のアンチエイジング戦略”の提案でもあります。
今回はそのエッセンスをこのアンチエイジング通信でわかりやすくお伝えします。

元産業大臣・元科学技術大臣: Dr. Atchaka Sibunruangとの写真
私たち(大友と河村)は元々、「痛み」を専門とするペインクリニシャンとしてキャリアをスタートしました。師匠である北原雅樹先生(現:横浜市大教授)から単に局所を治療するだけではなく、身体全体のバランス、そして心の状態や生活背景までを総合的に診る“全人的医療”の重要性を教えていただきました。
その過程で慢性的な痛みを抱える患者さんと向き合い続けていて、ある共通点に気づいたのです。
それは、「老化」というプロセスが、痛みの土台に存在しているということ。
脳機能のダメージも筋肉、神経や関節の炎症の背景には「エイジング」が静かに潜んでいることに気が付いたのです。
このことが、私を「加齢を治療する医療」=アンチエイジング医療へと導いてくれました。

2009年に私たちはアンチエイジングクリニックを開設しました。当時としても先進的でしたが、その当時はホルモン補充も点滴療法も、まだまだ特殊な医療とされていた時代。
それでもうわさを聞きつけてお越しいただける方に、その時代時代で可能な最先端の予防医療や若返り戦略をご提案してきました。
そんな日々をすごしていたところ、ある日突然、私自身の顔が赤く腫れ、ヒリヒリと焼けるような痛みに襲われたのです。
診断は「酒さ様皮膚炎」…どんなにステロイドを塗っても、抗生剤を飲んでも、レーザーやIPLを繰り返しても、まったく改善しませんでした。
恥ずかしながら、難治性疾患の“患者”になって初めて、病気に対する不安が実感として理解できました。
その後、友人の紹介でロサンゼルスのUCLA皮膚科教授であるヘン先生を訪ねたところ、開口一番こう言われました。
“それは皮膚の問題ではなく、腸に慢性的な炎症があるサインですよ”
検査の結果、乳糖不耐に伴うリーキーガット(腸管バリア機能の破綻)が判明しました。
皮膚に現れていた炎症のトリガーは、腸だったのです。 実は、IgGフードアレルギー検査で「乳製品を避けるべき」という結果は以前から出ていました。
しかし、大きな症状がなかったため、私は深刻には捉えていなかったのです。
乳製品を絶ち、教授が開発したウコンをベースにしたスキンケアを使うことで、症状は4ヶ月で落ち着いたわけです。
ちなみにこのスキンケアは、後に日本人向けにアレンジし、当院でご案内している「オムニキュア化粧品」として展開されています。
この経験を通じて私は、「腸」「食」「炎症」の密接な関係を、身をもって学びました。
炎症を鎮め、再生力を高めるためにライフスタイルを調整する――。
そんな食から始めるエイジングを治療するというコンセプトは、多くの患者さんに受け入れられました。
ただ、私も河村院長もからだに悪いだろうとわかっていて断ち切れていないものが一つあります。それはシャンパーニュとワイン。
ちなみに二人ともワインを啓蒙してきたこともご評価いただいて、シャンパーニュ、ブルゴーニュ、ボルドーの3つの騎士団からシュヴァリエの称号もいただいております。
患者さんからもよく聞かれます。「先生、お酒飲んでいていいのですか?」
正直に言うと、アルコールは慢性の炎症を引き起こし、細胞に明らかなダメージを与える可能性があります。
多くの方が心配されるがんのリスクも以下の通り、統計学的には上昇します。
・食道がん:5倍
・肝がん:2〜3倍
・乳がん:20〜50%
・大腸がん:20〜60%
それだけでなく心房細動→脳卒中のリスクや、前頭葉の萎縮→認知症のリスクも高まります。
しかし私は、そのリスクとどう向き合い、それから逃れる努力をしているかを医師としてお示ししたいと思っています。
私が提唱するのは、老化に対する「段階的・統合的」な3ステップアプローチです。
Step 1:慢性の炎症から細胞を守る(Protect Your Cells)
老化を引き起こす酸化ストレス、糖化ストレス、インスリン抵抗性、腸の炎症という4つの因子のダメージを可視化し、それを防御することが重要です。
腸のダメージと同じくらい大事なのが酸化ストレス。その一つの大きな原因が「環境毒素」です。
• 水銀(マグロなど)、鉛(排気ガス、農薬)
• PFAS・マイクロプラスチック、PM2.5(ダイオキシン)
• アルコール・タバコ
これらは酸化ストレスと慢性炎症を引き起こす「火種」となります。 ですので、まず行うべきは摂取量を減らすこととデトックスすること。
私自身は定期的に酸化ストレスをはじめとする慢性炎症を調べて、ビタミンCやグルタチオン点滴、CoQ10、アスタキサンチンをサプリメントでケアしています。
Step 2:細胞を再栄養して再生させる(Re-Nourish)
再生には材料とスイッチが必要です。
• 材料→ 栄養素(ビタミン、ミネラル、アミノ酸)
• スイッチ(Switches)→ ホルモン(テストステロン、DHEA、成長ホルモン、コルチゾール等)
ストレスや加齢により、ホルモンは簡単に落ち込みます。渋谷セントラルクリニックでは栄養素や ホルモンの状況を調べて、必要に応じて高いレベルに維持できるように補っています。
ホルモン補充は、「若返る」ためではなく、「壊れない」ための土台づくり。
実際、睡眠、気分、集中力、そして「人生の充実感」が大きく改善したことを実感される方も多いです。
なお、NAD⁺は高すぎてもリスクがあり、がんや神経変性疾患との関連も示唆されていますので、検査で最適値を把握した上での設計が重要です。
Step 3:細胞スイッチを巻き戻す(Rewind)
ここが現代医療の新領域です。人間のエイジング(老化)はパソコンやスマートフォンの場合と同じく、再起動が可能であり、ソフトウェアのように書き換えられる」と提唱しているのが ハーバード大学のDavid Sinclair教授。
そこで重要視されている一つの分子がNAD⁺。
• ミトコンドリアを活性化
• 長寿遺伝子(サーチュイン)をオン
• 遺伝子レベルでの修復
最新の研究ではNAD⁺が高すぎることは、がんや認知症につながるかもしれないという話もありますので、検査の上で適正な値にすることが重要です。
これまで、医療は「病気を見つける」ことに主眼を置いてきました。しかし、これからの医療は、病気になる前の「老化(エイジング)そのものを評価して、未然に病気を防ぐ」時代へとシフトし始めました。
当院では、この新しいアプローチを可能にするために、DNAメチレーション解析やエピジェネティック検査などの最先端の検査を取り入れてがんや認知症の超早期発見及び重大なリスクを事前に予測する取り組みを始めております。
「老化は避けられないものなのか?」という質問に対する私の答えは、 「いいえ、老化は、自分の意志でデザインできる時代に入った」というものです。
そのために必要なのは、自分自身の身体と向き合い、どう生きていきたいかを明確にすることです。
渋谷セントラルクリニックでは、皆さま一人ひとりのライフスタイルや価値観、将来のあり方を丁寧に伺い、科学的根拠に基づいた評価と介入を行っています。
✔精密な検査に基づいた、オーダーメイドの栄養・ホルモン補充
✔酸化ストレスや環境毒素に対する、個別最適化されたデトックス戦略
✔遺伝子やエピジェネティックなリスクを可視化し、未来の健康を見据えた予防策
✔必要に応じた、各専門領域の信頼できる医師との連携
私たちは、予防・再生・早期対応を一体として設計し、「変化に備えながら、いまを最善に生きる」ための医療を提供しています。

今月のお得なキャンペーンは「これからの長寿医療に向けてスペシャル企画!!」こちらからご覧ください